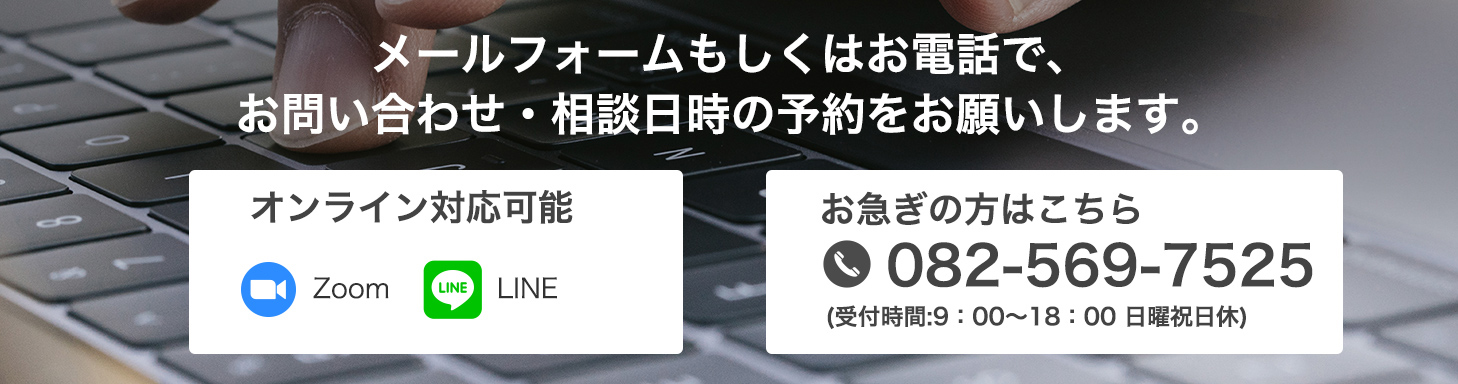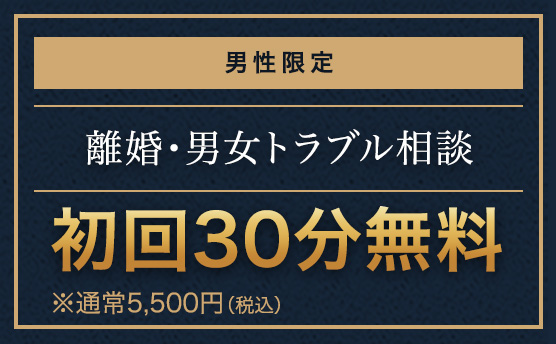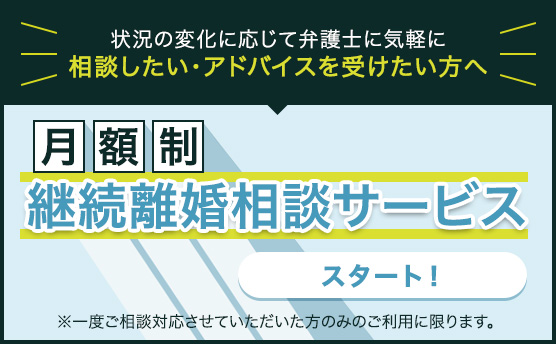別居以来,子供と会うことができません。会いたいのですが,どうすればいいでしょうか?

面会交流とは?
よく勘違いされやすいところですが,面会交流は「親の権利」ではなく子供の権利であると裁判例上では考えられています。また,家庭裁判所の手続きで面会交流が問題になる場合でも親同士の対立などが影響する点は事実上あるものの,同様に考えられています。
あくまでも,子供の健全な成長にとって,普段監護していない方の親と交流を持つことが好ましいから認められているものです。
そのため,ついそう言ってしまいそうですが,子供と会えないから養育費を払わないという話が通じるものでもありません。
面会交流とは,どのような場合に認められるの?
先ほど触れました事柄の性質上,子供にとって親との面会がプラスであれば認められるべき性質のものになります。とはいってもわかりにくい点があります。最近の傾向として感じている点からすれば,特に面会を制限するだけの事情がない限りは,面会交流自体は認める傾向にあるように思われます。あくまでも家庭裁判所での調停などでの話です。
こう言った場合に,そう簡単に面会交流が制限されるかというとそうはなりません。ただし,どのように面会交流を図るかは難しい問題です。子供に対する暴力や暴言がある・諸事情から面会交流をすると子供がひどく覚えることが明確などの事情があれば,当然面会交流の制限の可能性は出てきます。
また,非常に長い間会っていないことで子供が拒否的な反応を見せる場合にも何かしら面会交流の制限の可能性は出てきます。
子供と会えない場合にとる方法は?
ご本人同士で面会交流が難しい場合には,面会交流の調停の申し立てを家庭裁判所ですることが考えられます。以前に離婚調停などで面会交流の条項があるものの守られない場合には,履行勧告という制度を使う方法もあります。ただし,強制力はありません。場合によっては再度面会交流の調停を申し立てるケースもありえます。
家庭裁判所の調停では,状況等に応じて家庭裁判所調査官の調査が行われる・家庭裁判所内での試行的な面会交流が行われる可能性があります。話し合いがつかない場合には,審判に移行し裁判官による判断が下されます。
面会交流の難しい点
面会交流がなかなか実現できない場合の一番難しい点は,実現へ向けての第1歩をどのように確保していくかという点かと思われます。
背景事情はケースごとに様々ですが,別居までの子育てへの関与や夫婦の間の不信感,別居後の不信感(ことに離婚前の面会交流)等様々な事情がマイナスに影響している可能性があります。
親同士の不信感が子供にとって面会交流への負担につながる場合もありますので,ある程度の信頼感の確保は重要になってきます。もちろん,さしたる根拠なく会わせたくないという場合には別ですが,こうした信頼感を確保しながら,実際に会うことへとつなげていく点は調停であっても変わりはないものと思われます。
面会交流が制限される場合はそれなりの事情が必要という点を先ほど記載しましたが,そうはいってもとりあえず負担を子供にかけないために,まずは間接的な交流を図るということ自体はありえます。こうした方法には手紙やメールのやり取り等ありますが,少しずつ形を作っていくというイメージで取り組むことがご自身にとって一番負担が少ないのではないかと思われます。
面会交流は,まず会う形を作るのに難しい点があるのには注意が必要でしょう。